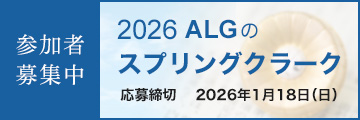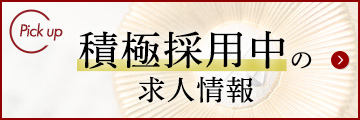私の就職体験記弁護士 阿久津 航
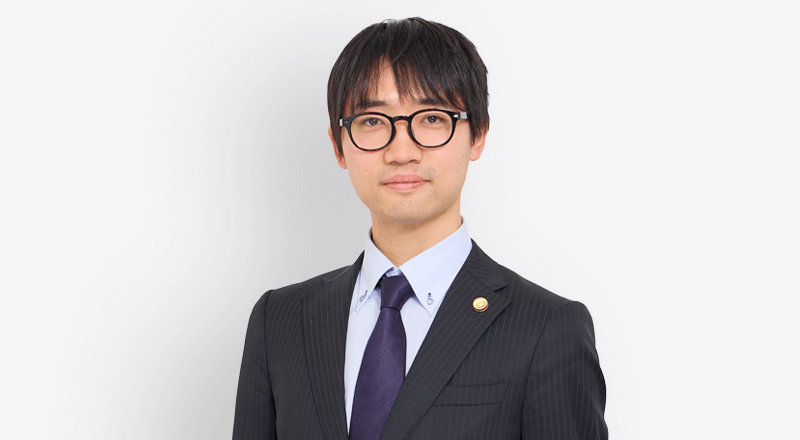
千葉法律事務所 76期 弁護士 阿久津 航 (千葉県弁護士会所属)
■就活を行った時期
一般的に、法律事務所の就活情報が多く流通する時期は、大きく3つに分かれるかと思います。
具体的には、
- 第1ウェーブ 司法試験終了後~
- 第2ウェーブ 司法試験合格発表後~
- 第3ウェーブ 司法修習開始後~
の3段階のウェーブがあります。
一般民事系の事務所よりも、企業法務系の事務所の方がより早く情報解禁される印象です。
私が就活を行っていた頃は、いわゆる「売り手市場」でしたが、早く動き出しをしておかないと採用枠が埋まってしまうのではないかという不安から、私は第1ウェーブ期から既に就活を開始していました。
朝井リョウさんの『何者』を読んでいたため、異様に危機感を煽られていたせいもあるかもしれません。
いずれにせよ、早く動き出しておくにこしたことはないかと思います。
■就活内容
就活といっても何をすればよいか全くわからなかったため、ロースクールのキャリア支援制度を利用しました。
エントリーシートの添削をしてもらったり、模擬面談をしてもらったりと、今思い返すと少し恥ずかしいような、「模範的」な就活生だったと思います。
主にやっていたこととしては、
- 事務所説明会に参加(20~30くらいの説明会には参加しました)
- そのうち気になった事務所に訪問(5、6くらいの事務所に訪問してます)
等でした。
法律事務所への就職は、伝統的に「一人前の弁護士になるための修養の一過程」として考えられてきたため、ややブラックボックスと言いますか、どのような視点で就活したらいいのか、その後のキャリアプランをどう構築したらいいのかの見通しを立てづらいかと思います。
そのような中で、参考になった書籍は下記のものでした。
- 西田章『新・弁護士の就職と転職 キャリアガイダンス72講』
長期的なキャリアプランニングを考えるうえで抜群の威力を発揮します。ただ著者が企業法務系事務所の出身であるためか、一般民事系事務所に関する記述は物足りないように思いました。 - 野村慧『新版 弁護士・法務人材 就職・転職のすべて』
各キャリアのメリット、デメリットが詳しく書かれており、参考になります。 - 北周士『弁護士独立のすすめ』
独立弁護士の苦労がかなり詳しく(事務所設立に必要な予算に至るまで!)解説されているため、涙なしでは読めません。仮に独立を考えていなかったとしても、面白く読めると思います。 - 瀧本哲史『僕は君たちに武器を配りたい』
法律事務所の就活とは直接関係しないのですが、これも名著です。競争の激しい時代をサバイブしていくために、どのようなマインドで就活をしたらいいのか、異様な明晰さで解説してくれます。
■就活方針
前置き(?)が長くなりましたが、私の就活方針について説明します。
私の頭の片隅には、「弁護士数が今後増えていくなか、どのような法律事務所であれば生き残っていけるだろうか」という問題意識が常にありました。
いろいろと検討してみましたが、やはりマーケティングの観点から、集客力がある事務所であることが第一の要件になるだろうと考えました。
主要な事務所のホームページを分析してみますと、ALGには
- 事業部制を採用していること
(それにより高い専門性が担保されていると思われること) - 弁護士数が多いこと
(2025年時点で、全国トップ20には入るくらいの規模感です)
等の特徴があり、依頼者からは魅力的に見えるのではないかと思われました。
加えて、弁護士として広い裁量をもって仕事を行えることが、事務所選定の第二要件になると考えておりました。
弁護士の仕事の魅力は何よりも、「自分ですべて責任をもって、自分の判断で仕事を遂行できること」にあります。
世の中には、事務所の都合により個々の弁護士の仕事のやり方に対し強い圧力がかかるような事務所もあるかもしれませんが、事務所説明会や事務所訪問を通して、ALGであればその点心配がないだろうと考えました。
クラーク中に所内の先生が作成した法律記録をみたり、実際に話を聞いたりしていくなかで、その考えは確信に変わっていきました。
(実際に働いてみて、自分の直感は間違っていなかったと実感しています)。
そのほか事務所の雰囲気や労働時間、通勤時間、報酬などの諸要素を総合的に考慮しました。具体的には、考慮要素ごとに1~5点の重みをつけて、それに1~5点の得点を掛けて、総合得点をエクセルにまとめていたと記憶しています(なぜこんなに細かくて面倒なことをやっていたのか、今では不思議です……)。
その結果、第一志望であったALGにエントリーし、無事に採用していただいて今に至ります。
※2025年7月末日時点でのインタビュー内容です