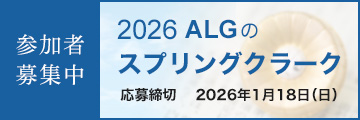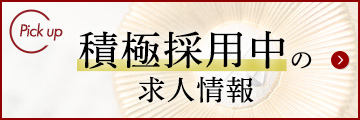私の就職体験記弁護士 齋藤 一真

東京法律事務所 民事・刑事事業部 76期 弁護士 齋藤 一真 (東京弁護士会所属)
①就活の開始時期
今日の司法試験受験生は、就活の早期化の潮流を受け、半数近く、あるいはそれ以上の方が司法試験の合格発表前に就活を開始し、中には就活を終えられる方もおられるようなイメージです。
かくいう私の世代も上記のような潮流を少なからず受けており、同級生の多くが司法試験合格発表前から法律事務所の弁護士採用選考にエントリーしているのを目の当たりにしていました。
一方で、私はと言いますと、実際に履歴書を送ったり、面接を受け始めたのは、司法修習が開始してからになります。
②遅めの就活開始
案の定、修習がスタートすると大半は内定先事務所が決まっており、同期との間では就活の話題にすらなりません。正直、修習が開始してもなお就活を開始しておらず、内定先が決まっていないことに羞恥と焦りを感じていました。
そもそも、就活の開始が遅れたのは、令和4年度司法試験の公法系科目(憲法)で設問の取違いをしてしまい、司法試験受験後は不合格を確信したため、ひたすら現実から目を背けていたという経緯があります。
結果として、何とか司法試験に合格しましたが、その頃には周囲の同級生の大半は就活を終えていたこともあってか、劣等感が先行し、就活への意欲が湧きませんでした。これは、私が司法試験の勉強を始めた頃から検察官志望だったということも影響していると思います。
すなわち、「就活の開始は遅れたし、内定先もないけど自分は検察官になるから」と高を括っていたように思います。
しかしながら、修習が始まり、検察官のリクルートも流れるように開始していくわけですが、その中で検察官の内定には少なからず弁護士事務所の内定を持っていることが必要との情報に接するようになりました。
以上のような経緯で、私もいよいよ就活を開始しました。
③法律事務所の選び方
私は、決して要領の良い方ではなく、同じ作業をするにしても人より時間がかかってしまうきらいがあります。そのため、いわゆるジェネラリスト的な働き方をしていては、いずれの分野の業務も停滞してしまうことが予想されたため、事務所選びに当たってはある程度スペシャリスト育成にベクトルが向いているか否かという点を重視していました。
その中で、刑事事件特化型の事務所等の選考にもエントリーをしましたが、最終的には受験生時代、家族法の判例集を読んで“無味乾燥な教科書的文章なのになぜか感じる、人間の生々しいドロドロした情念”に好奇心を掻き立てられていた私は、離婚事件を中心に取り扱う弁護士になりたいと考えるようになりました。
補足すると、上記のような好奇心の延長で司法試験の選択科目は、国際関係法(私法系)を選択し、国際家族法の学習に勤しんでいました。
方向性が決まってから、事業部制採用の下、各弁護士が特定分野の事件を集中的に担当して、スペシャリストを育成する弊所(とりわけ、家事事件に注力する民事・刑事事業部)との出会いまではあっという間で、ご縁もあり入所するに至りました。
④さいごに
時代の潮流もありますが、慌てて就活に着手する必要まではないと思います。
まずは、ご自身の自己実現のためのエッセンスをピックアップするところから始め、しっかりその筋道を立てることが重要です。このプロセスなくして快適な弁護士ライフを送ることはおよそ不可能です。
ご自身を事務所のニーズに無理やり合わせて入所した事務所で過ごす弁護士ライフほど窮屈なものはないでしょう。そして、弁護士の自己実現と顧客の満足は表裏の関係にあります。そのため、窮屈な事務所で過ごす弁護士が提供するリーガルサービスの質は、快適な事務所で過ごす弁護士が提供するそれに一段劣り、ひいては、顧客満足も得られないものと考えます。
弊所の理念が「顧客満足」ではなく「顧客感動」なのは、各弁護士が自己実現を図ることができていることを如実に示すものです。
ぜひ一度、充足感に満ちた弁護士の姿を見に来られてはいかがでしょうか。
※2025年7月末日時点でのインタビュー内容です